エリオット波動理論は、テクニカル分析の一部として広く使われている重要なツールの一つです。
エリオット波動理論は、Ralph Nelson Elliottによって提唱されたテクニカル分析の手法です。この理論は、市場の価格動向を規則的な波動パターンとして捉え、その波動を分析することによって将来の価格変動を予測しようとするものです。
この記事ではエリオット波動について詳しく説明していきます。
エリオット波動理論の基本
エリオット波動理論は、上昇波動と下降波動の2つの基本的な種類の波動で構成されます。上昇波動は市場が上昇トレンドにあるときに現れ、下降波動は市場が下降トレンドにあるときに現れます。

5つの上昇波動
エリオット波動理論では、上昇トレンド中の波動を5つの波動で構成されるものと考えます。これらは、1から5までの数字で識別され、1, 3, 5番目の波動は上昇波動で、2, 4番目の波動は下降波動です。
3つの下降波動
下降トレンド中の波動は、3つの波動で構成されると考えられます。これらも1から3までの数字で識別されます。1, 3番目の波動は下降波動で、2番目の波動は上昇波動です。
波動の比率
エリオット波動理論では、波動間の比率が重要視されます。たとえば、2番目の波動の高さは1番目の波動の高さの約61.8%になることがよく見られます(ゴールデン・レシオと呼ばれるもの)。このような比率は、波動の相対的な長さや強度を示すのに役立ちます。
波動の組み合わせ
エリオット波動理論において、これらの基本波動が組み合わさり、複雑な波動構造を作り出すと考えられます。これらの組み合わせは、エリオット波動のパターンとして認識され、さまざまなトレンドの形成と転換を示すのに役立ちます。
エリオット波動の周期性
エリオット波動理論は、どの市場でも適用できるとされており、異なる時間枠で波動を分析することができます。つまり、短期の日足チャートから長期の週足チャートまで幅広い時間枠で利用できます。
エリオット波動3原則
エリオット波動には以下の3原則があります。

原則①:推進波において3波は1波、3波、5波の中で最も短くはならない
この原則は、推進波(衝撃波またはインパルス波)の内部での波動の長さに関するものです。具体的には、推進波は3つの上昇波動(1波、3波、5波)および2つの下降波動(2波、4波)から構成されるが、これらの波動のうち、3波は1波、3波、5波の中で最も短いものにはなりません。
原則②:推進波の中で2波が1波の始点を超えて修正することはない
この原則は、推進波内の2波と1波の関係に関連しています。2波は1波の始点を超えて価格を修正しないという意味です。これは、推進波がトレンドの強さを示すものとして考えられます。
原則③:推進波の中で4波が1波の高値を割り込むことはない
この原則は、推進波内の4波と1波の関係に関連しています。4波は1波の高値を割り込むことがないという意味です。これは、推進波が持続的なトレンドを示すものとして考えられます。
これらの原則は、エリオット波動理論において、トレンドのパターンと転換点を特定し、市場の価格動向を予測するためのガイドラインとして使用されます。エリオット波動理論は、市場の波動を理解し、トレード戦略を構築するのに役立つ強力なツールとされています。
エリオット波動とフィボナッチ比率
エリオット波動理論は、フィボナッチ比率の黄金比を基にしており、この理論を活用することで波動の転換点を予測することが可能です。フィボナッチ比率は自然界や生命の起源、また人間が美しいと感じる黄金比として広く知られており、市場やチャートの分析においても集団心理が影響を与え、自然に現れる要素と考えられています。そのため、チャートの分析においてはフィボナッチ・リトレースメントと組み合わせて使用されることが一般的です。
このアプローチによって、トレーダーやアナリストは市場の価格動向における重要な支持と抵抗のレベルを特定し、価格がどのように反応するかを予測できます。フィボナッチ比率は、エリオット波動の理論と組み合わせて、市場の波動をより詳細に分析し、トレンドの進行や反転ポイントを見極めるのに役立ちます。
このアプローチは、テクニカル分析の一部として広く採用され、市場の価格動向を予測するための重要なツールの一つとされています。
エリオット波動の押さえておきたい特徴
エリオット波動理論の基本原則を理解したら、次は波動のパターンとチャートパターンに焦点を当ててみましょう。これらの波動パターンは、チャートパターンの構成要素として働き、市場の価格動向をより詳細に分析するのに役立ちます。基本原則を理解した後、波動パターンを学び、最終的にはチャートパターンとの関連性を把握することで、エリオット波動理論に対する深い理解を深めることができます。
6つの波動
・I波動
上昇もしくは下降のみを表す1本の線で表されるシンプルな波動です。I波動を形成したあとにV波動となる傾向があります。
・V波動
V波動はI波動が2つ連続して形成される波動です。V波動はI波動のあとに形成され、N波動などに繋がるケースがしばしば見られます。
・Y波動
Y波動は逆三角形のペナントを形成する波動で後述するP波動の逆の波動です。徐々に値幅が大きくなっていくため、高値・安値を更新しながら拡大三角を形成していきます。つまり、高値→安値→高値→安値→高値→安値を更新しながらペナントを形成するということです。エントリー難度が非常に高く、トレード上級者でもY波動に関してはトレードを控える傾向にあります。
・P波動
P波動は三角形のペナントを形成する波動で三角持ち合いと呼ばれる状況で出現します。形成されたのちはN波動への繋がりが考えられます。
・N波動
N波動は上昇・下降の値幅が等しい波動のことです。N波動は最も基本的な波動で、このN波の中に様々な波動が形成されるパターンが殆どです。レンジ相場や上昇・下降トレンドの発生時にもN波は形成されます。
・S波動
S波動は高値(安値)更新した後に修正波が入った場合に、前回の高値(安値)がサポート・レジスタンスとして機能し再び反発後、高値(安値)をつけにいく波動です。 N波動後に反発し、形成されるケースが多いです。高値(安値)を連続で更新するので強気のトレンドが発生している際に形成される傾向にあります。
よく見られるトレンド回帰型のチャートパターン
・トライアングル
トライアングルは、価格の上昇と下降の幅が次第に狭くなり、三角形の形を描きながら横ばいの波動となるチャートパターンです。通常、価格が収束していきますが、その形状に応じて上昇型トライアングル、下降型トライアングル、拡大型トライアングル、ランニングトライアングルなどの異なる種類に分類されます。
・ブロードニングフォーメーション
ブロードニングフォーメーションは、最高値と最安値が交互に更新されながら拡大していく波動です。逆三角形の形状をしており、Y波動と似た形状を持ちます。通常のトライアングルとは異なり、取引量や参加者が徐々に増加している状況で形成されることがあります。そのため、このパターンは市場の天井で形成されることが多いとされています。
・ペナント
トライアングルとほぼ同義です。
・フラッグ
フラッグパターンは、高値と安値を結ぶ長方形の中で価格が上下動し、均衡状態を保っている形状を指します。通常、このパターンは典型的なレンジ相場の特徴を示していますが、価格が上昇または下降方向に進展する傾向があります。フラッグパターンは、急激な価格変動の前に形成されることが多い特徴も持っています。
・ウェッジパターン
ウェッジパターンは、価格の幅が狭い範囲で持続的に続く波動です。ウェッジは通常、トライアングルやペナントに比べてより急な角度で価格パターンが形成されます。このパターンは、比較的静かな市場状況で形成されがちですが、エネルギーが蓄積されており、反発時に急激な動きが起こる可能性があります。
よく見られるトレンド転換型のチャートパターン
・ダブルトップ、ダブルボトム
ダブルトップは、トレンドの終わりに形成される波動で、通常、上昇トレンドの終わりに出現します。このパターンでは、価格が2つの山を形成し、3波と5波の山がそれぞれトップを形成します。2回の価格の高値が近くにあり、その後価格が下落することが特徴です。ダブルトップはトレンド反転の兆候とされます。
ダブルボトムは、トレンドの終わりに形成される波動で、通常、下降トレンドの終わりに出現します。このパターンでは、価格が2つの谷を形成し、2波と4波の谷がそれぞれボトムを形成します。2回の価格の安値が近くにあり、その後価格が上昇することが特徴です。ダブルボトムはトレンド反転の兆候とされます。
これらのパターンは、トレンド反転のポイントを示し、トレーダーやアナリストに価格の変動を予測する手助けをします。
・ヘッドアンドショルダー
ヘッドアンドショルダーパターンは、3つの山が形成される波動です。このパターンの特徴として、真ん中の山が最も高くなる点が挙げられます。ヘッドアンドショルダーパターンは通常、トレンド時に発生し、価格反転のサインとされます。
・ラインパターン
ラインパターンは、ライントップと呼ばれる山の頂点が同じ価格レベルに位置している波動です。このパターンは、相場が横ばいの状態にあることを示します。通常、相場の天井で発生し、ラインパターンの場合、1波、3波、5波の3回の天井が同じ水準に達することに注意が必要です。
・ソーサ―
ラインとほぼ同じ状況で出現しますが、天井が直線ではなくおわん型の曲線となっていることが特徴の波動です。
エリオット波動理論の活用法
エリオット波動理論を取引に活用する際の戦略や方法について説明します。
1. トレンドの発生を捉える
エリオット波動理論を活用する際には、まずトレンドの発生をチャートから読み取ります。波動の基本形であるN波を見つけて、トレンドの発生とその方向(上昇または下降)を把握しましょう。
2. 利益確定と損切りのタイミングを考える
エリオット波動は値幅と方向感の分析に役立ちます。したがって、利益確定ラインや損切りライン、およびそのタイミングを考える際に参考になります。他のテクニカル指標と組み合わせて使用して、トレードの根拠を強化しましょう。ただし、過度な信頼はせず、ラインでの反発が確実とは限らないことを念頭に置いてください。
3. 3波の波に乗る
エリオット波動を用いた最もシンプルなエントリー方法は、3波に乗ることです。3波は全体の5波のうちで最も上昇または下降幅が大きく、大きな利益を狙えるメリットがあります。具体的なエントリータイミングは、2波の途中で1波の高値(または安値)を超えるときです。このポイントの高値(または安値)の突破が本物かどうかを確認することが重要です。また、利益確定のタイミングは3波の終盤が適しています。
4. 4波の波に乗る
もうひとつのシンプルなエントリー方法は、4波に乗ることです。4波では、3波とは逆のサイドに注文を出すことで、下降(上昇)局面でも利益を狙うことができます。ただし、4波は3波に比べて値幅が小さいため、5波の推進波が到来する前に利益確定することを忘れないようにしましょう。
5. フィボナッチ・リトレースメントとの組み合わせ
エリオット波動理論を活用する際に、フィボナッチ・リトレースメントと組み合わせて使用することが効果的です。フィボナッチ・リトレースメントは高値と安値の値幅にフィボナッチ比率を適用したもので、反転ポイント(サポートとレジスタンス)を特定するのに役立ちます。23.6%、38.2%、50.0%、61.8%、76.4%などの比率に自動的にラインが引かれるため、視覚的にも反転ポイントを判断しやすくなります。
これらの方法を組み合わせて、エリオット波動理論をトレードに活用することで、より正確なトレードの意思決定が可能になります。ただし、エリオット波動理論は主観的な要素が含まれるため、確度を高めるために他のテクニカル分析やリスク管理戦略と組み合わせて使用することが重要です。
まとめ
エリオット波動について、イメージがわいたでしょうか?プロトレーダーの中には、エリオット波動を観察し、相場のサポートとレジスタンスポイントを特定して取引を行う人もいます。しかし、エリオット波動は一般的にFX初心者向けではなく、比較的上級者向けのテクニカル指標です。したがって、FXを始める予定の方や初心者の方は、まずは基本的なテクニカル指標を学び、マスターすることをお勧めします。基本的なテクニカル指標をしっかり理解した後に、エリオット波動を含む高度な分析手法に挑戦してみると、より成功の可能性が高まるでしょう。
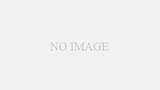
コメント